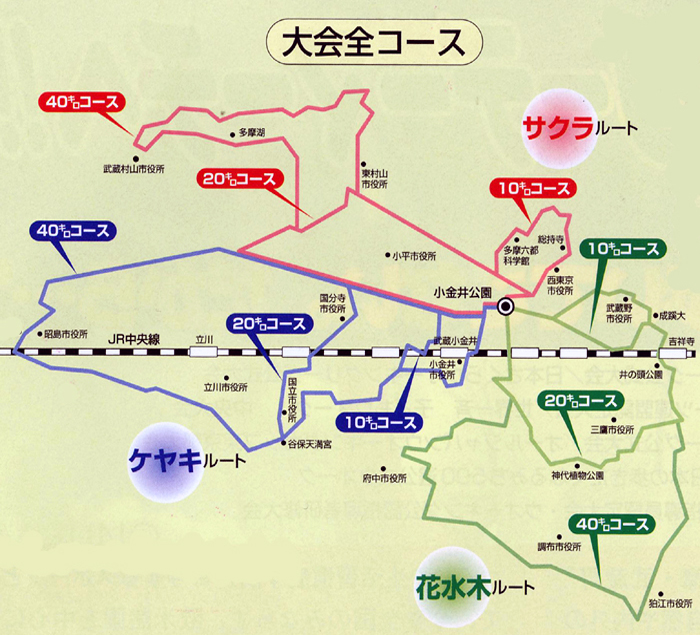
HOME > ウオーキング > 第12回 東京国際スリーデーマーチ
サクラルート 小金井公園から 多摩湖、玉川上水方面を一周 40,km, 20km, 10km, 5km コース
ケヤキルート 小金井公園から 国分寺、野川方面を一周 40,km, 20km, 10km, 5km コース
花水木ルート 小金井公園から 井の頭、多摩川方面を一周 40,km, 20km, 10km, 5km コース
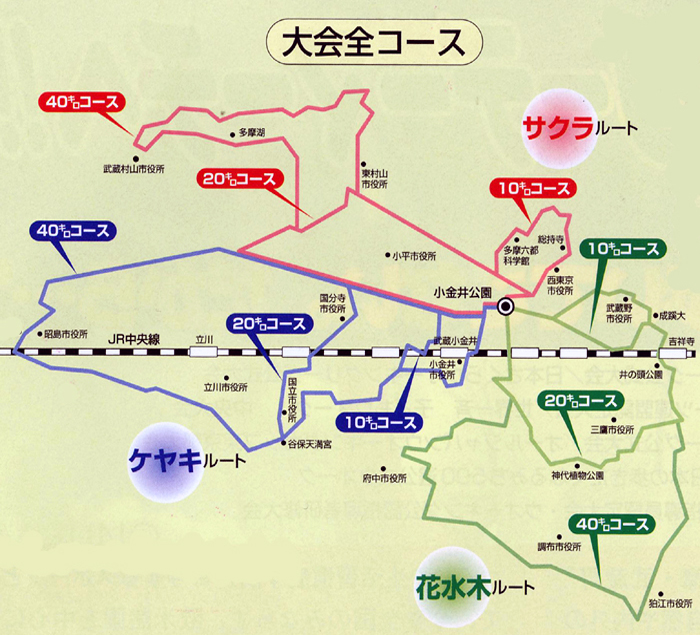
 スタート、ゴール会場の小金井公園 |
 小金井公園 |
 小金井公園「いこいの広場」で出発準備 |
 小金井公園 ルート毎に整列 |
 小金井公園中央ステージ |
 小金井公園 いよいよサクラルートスタート |
 サクラルートをスタートした。 |
 |
 |
 |
 途中の案内板。 |
 |
 |
 |
 ゴール、サクラルート |
 小金井公園 |
 小金井公園 |
 小金井公園にて昼食後ちゅうしょj |
 ゴールに続々到着 |